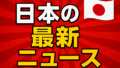今回のジジポリでは、コロナ禍で明らかになった日本の大学の対応格差と、「幻滅大学」と呼ばれる大学の実態について解説していきます。
① 導入:大学の価値が問われる時代に
新型コロナウイルスの流行は、大学教育の在り方を大きく変えました。
リモート授業が当たり前となり、「授業料は変わらないのに内容は劣化した」と感じた学生が増え、退学を考える人も少なくありません。
中には、学生に寄り添い柔軟に対応した「優良大学」もあれば、形式的な対応に終わった「幻滅大学」も存在します。
この違いは、単なる設備や財政の問題ではなく、大学の姿勢やリーダーシップの差だと指摘されています。
② 概要:優良大学と幻滅大学の違い
社会学者・佐藤郁哉氏(同志社大学教授)は、次のように大学を分類しています。
- 優良大学:学生の生活や学習環境を第一に考え、早期に経済支援・オンライン対応を実施
- 幻滅大学:できない理由を探し続け、学生への対応が遅れた大学
たとえば、天理大学では3月の段階で全学生に電話連絡を行い、通信環境を調査。
大阪大学もWi-Fiルーターの無償貸し出しや経済支援など、学生を支える施策を迅速に展開しました。
一方で、一部の大学では「ホームページに情報を載せただけ」で、学生に必要な支援が届かないケースも多発。
この差が、今の「退学希望者増加」という深刻な結果を招いています。
③ 専門用語解説:「幻滅大学」とは?
「幻滅大学」とは、コロナ禍で学生が抱いた期待を裏切った大学のこと。
オンライン授業の準備不足や経済支援の遅れなどから、学生に「この大学に入った意味がない」と感じさせてしまう学校を指します。
この背景には、佐藤教授が指摘する「機械的な大学運営」があります。
機械的運営とは、組織の規模拡大に伴い、学生よりも内部調整や事務手続きが優先される体質のこと。
つまり、大学が**「学びの場」ではなく「管理の場」**になってしまっているのです。
④ 影響と今後の対応:大学の存在意義が問われている
コロナ禍をきっかけに、大学の「存在意義」が改めて問われています。
オンライン講義が普及し、知識の授業だけなら他大学の講師の動画でも代替可能です。
では、大学の価値とは何か?
それは、学生が自ら考え、新しい知識を生み出す力を育むことにあります。
同志社大学の創設者・新島襄は、生涯を通じて「倜儻不羈(てきとうふき)=権力に盲従せず信念を持つ人材」を育てることを理想としていました。
今の大学が目指すべきは、まさにこの「自分で考え、行動できる人材」の育成です。
しかし現状では、「できない理由」を並べるだけの大学が多く、社会の変化に対応できていません。
今後、大学が生き残るためには次のような取り組みが必要でしょう。
- 学生一人ひとりの学びに寄り添うサポート体制
- 透明性のある情報発信と迅速な意思決定
- 教員・学生・社会の三者が協働する教育モデルの確立
⑤ 読者への問いかけ
もしあなたが学生だとしたら、「この大学に通い続けたい」と思える環境はどのようなものでしょうか?
また、保護者や社会人として、今の日本の大学にどんな教育を期待しますか?
大学の「機械的運営」が続く限り、教育の未来は閉ざされるかもしれません。
まとめポイント
- コロナ禍で大学間の対応格差が浮き彫りに
- 「幻滅大学」とは、学生支援に消極的な大学のこと
- 優良大学は、経済・精神両面から学生を支援
- 大学の存在意義は「自ら考え行動できる人材」を育てること
- 日本の大学は「機械的運営」から脱却する必要がある
(出典:共同通信「退学希望者が続出「幻滅大学」の酷すぎる実態 コロナで浮き彫りになった格差」