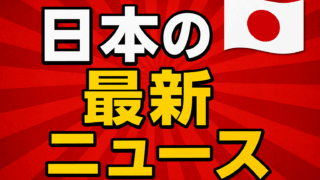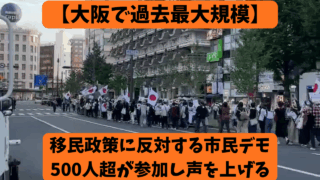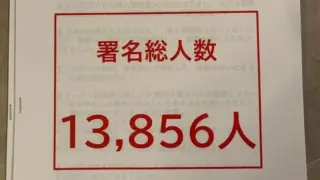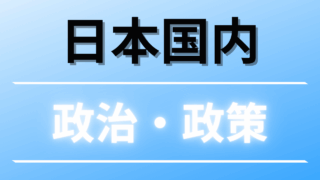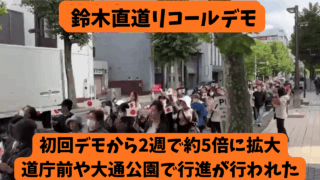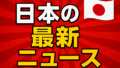佐賀県警の科学捜査研究所(科捜研)で、過去7年以上にわたりDNA鑑定の不正が行われていたことが明らかになりました。刑事事件の証拠として決定的な役割を果たすDNA鑑定の信頼性が揺らぐ今回の事件は、私たちの司法制度全体に関わる重大ニュースです。なぜこうした不正が起きたのか、県警の対応は妥当なのか、そして「さば県警」と揶揄される背景について詳しく解説します。
事件の概要──DNA鑑定不正の実態
佐賀県警科捜研に所属していた40代の技術職員は、2024年までの約7年間にわたり、DNA型鑑定で次のような不正を行っていました。
- 未実施の鑑定を「実施済み」と偽って報告
- 紛失資料を偽造して返却
警察庁は2025年10月2日、特別監察を実施すると発表。130件の不正のうち、特に悪質と認定された13件については、虚偽有印公文書作成や証拠隠滅で書類送検されています。職員本人は「早く仕事を終わらせて評価を上げたかった」と不正の理由を説明しています。
特別監察とは何か
今回の調査は「特別監察」と呼ばれるもので、警察庁長官が責任者として行う臨時の内部調査です。記録が残る2011年以降、過去には4件しか実施されていません。
しかし、専門家や弁護士会からは、「内部調査だけでは公平性や中立性が担保されない」という指摘が出ています。佐賀県弁護士会は「第三者を入れない調査で幕引きを図ろうとしている」と批判し、県議会も全会一致で第三者調査を求める決議を可決しましたが、県警は「守秘義務の関係で第三者による調査はなじまない」と拒否しています。
「さば県警」と揶揄される理由
佐賀県警は過去にも杜撰な捜査で批判を受けたことがあります。
- 1989年:北方事件
女性3人の遺体が発見された事件で、無実の男性が逮捕されるなどの不手際があった。 - 2019年:暴行死事件
遺族からの批判を受け、女性初の本部長が交代に追い込まれる。
こうした経緯から、県警は「事件をうまくさばけない」として、他県から「さば県警」と揶揄されることもあります。
なぜ今回の問題は重要なのか
DNA鑑定は「証拠の切り札」とされるほど、刑事事件の判断に影響します。もし鑑定結果が不正であれば、無実の人が逮捕・起訴される可能性もあります。
今回の事件は、司法制度の信頼性を揺るがす深刻な問題です。警察組織が透明性を持って説明しないと、国民の信頼はさらに低下してしまいます。
私たちに何ができるのか
- 警察の説明や調査の結果を注視する
- 第三者調査の必要性を社会全体で議論する
- 刑事司法制度の透明性向上を求める声をあげる
あなたはどう思いますか?DNA鑑定の信頼を取り戻すために、県警はどのような行動を取るべきでしょうか。
まとめポイント
- 佐賀県警科捜研で7年以上にわたりDNA鑑定不正が発覚
- 130件の不正のうち13件は書類送検される重大事案
- 特別監察は実施されるが、第三者調査は拒否
- 過去の杜撰な捜査で「さば県警」と揶揄される歴史がある
- DNA鑑定の信頼性は刑事司法の根幹に関わる重要課題
(出典:Yahoo!ニュース「過去には無罪の男を逮捕したことも…佐賀県警が他県から“事件をさばけん”と揶揄されてしまうワケ《DNA型鑑定の不正が判明》