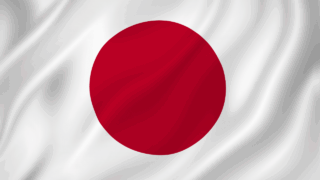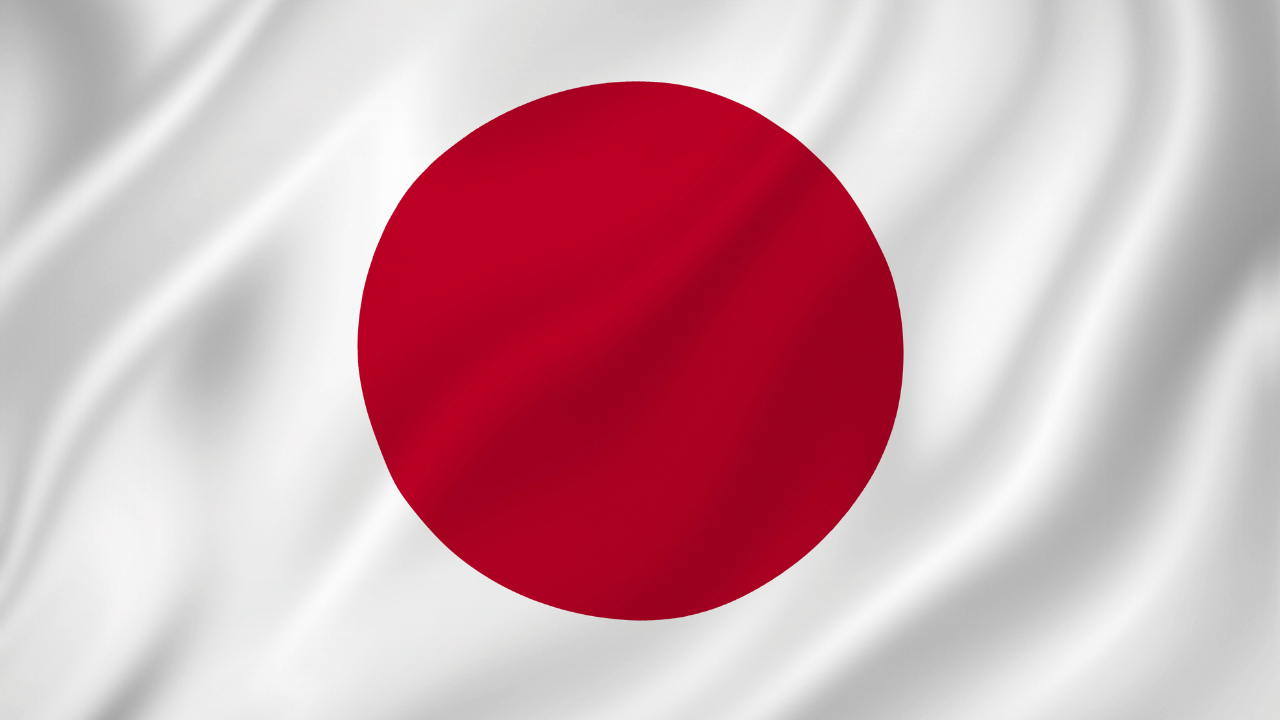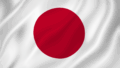2025年10月、国内の主要食品メーカー195社による家庭用飲食料品の値上げが3024品目に上り、半年ぶりの大規模な値上げラッシュとなりました。1回あたりの値上げ率は平均で17%に達し、前年同月(2924品目)と比べて100品目の増加、割合にして3.4%の増加となりました。この傾向は10カ月連続で前年を上回る結果となり、統計が開始された2022年以来、最長の連続増加期間を更新しています。さらに、単月での値上げ品目数が3000品目を超えたのは4月(4225品目)以来、半年ぶりのことです。
値上げ対象の分野別状況
10月の値上げを食品分野別に見ると、**「酒類・飲料」**が最も多く、2262品目に上りました。これは焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心とした値上げで、単月で2000品目を超えたのは2023年10月以来、2年ぶりのことです。
次いで、**「加工食品」は340品目で、包装米飯や餅製品を中心に値上げが行われました。また、「調味料」**は246品目で、焼肉のたれや味噌製品が値上げ対象となっています。
2025年通年での値上げ動向
2025年の通年で見た場合、12月までに公表された値上げ累計は2万381品目に達し、前年実績(1万2520品目)を62.8%上回る大幅増となりました。これは2023年以来、2年ぶりに2万品目を超えた状況です。1回当たりの値上げ率は平均15%と前年(17%)よりやや低下していますが、依然として高水準が続いています。
食品分野別では、**「調味料」が6148品目で最も多く、前年(1715品目)から大幅に増加し、前年比258.5%増となりました。また、「酒類・飲料」**も4871品目と広範囲に値上げされ、ビールや清酒、焼酎、ワイン、清涼飲料水などが含まれ、前年比で8割以上の増加となっています。
値上げの背景と要因
今回の値上げの背景には、複数の要因が絡み合っています。主な要因は以下の通りです。
- 原材料高騰:全体の96.1%を占め、値上げの最大の要因となっています。
- エネルギーコストの上昇(光熱費):64.3%
- 包装・資材費の上昇:62.9%
- 物流費の増加:78.8%
- 人件費の増加:50.2%
特に物流費と人件費は前年より大幅に増加しており、製造・流通にかかるコスト上昇が価格に転嫁されていることがうかがえます。一方で、円安による値上げは12.4%にとどまり、前年より大幅に低下しているため、国内の内的要因による物価上昇が顕著になっています。
消費者への影響と中立的な視点
今回の値上げラッシュは、特に家庭での食費に直結する調味料や加工食品の価格上昇を意味します。アルコールや飲料も値上げ対象となることで、家計への負担は増すことが予想されます。ただし、企業側の立場としては、原材料費や物流費、人件費の上昇を吸収できないため、値上げは避けられないという背景もあります。
そのため、中立的に見れば、消費者の生活コストの上昇と企業のコスト圧迫という双方の事情が重なった結果と理解することができます。
まとめ:2025年10月の飲食料品値上げポイント
- 10月の値上げは3024品目、半年ぶりに3千品目を超え、平均値上げ率は17%。
- 値上げ対象は主に酒類・飲料(2262品目)、加工食品、調味料。
- 2025年通年では累計2万381品目が値上げ、前年より62.8%増。
- 主な値上げ要因は原材料費高騰、物流費・人件費増加、光熱費上昇。
- 円安の影響は低下、内的コスト上昇が価格に反映される傾向。
- 消費者負担増と企業コスト圧迫の両面が背景にあり、中立的には「内的要因による物価上昇」が主因と考えられる。
- 年末にかけては値上げの勢いがやや落ち着く可能性があるものの、2025年全体では高止まりの状況が続く見通し。