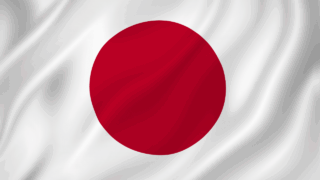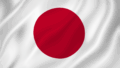国勢調査員とは?
5年に一度行われる「国勢調査」は、日本に住む全ての人と世帯を対象に実施される重要な国の統計調査です。調査の担い手となるのが、非常勤の国家公務員として任命される「国勢調査員」です。調査員は地域ごとに割り当てられ、一軒一軒の世帯に調査書類を配布・回収し、未回答の世帯には再度訪問するという役割を担います。
広島市だけでも毎回7,000人以上の調査員が必要とされ、全国では数十万人規模で動員されます。報酬はおおよそ50世帯で5万円程度とされ、年金生活者や地域の住民から引き受ける人が多いのが実情です。
しかし、その仕事は想像以上に負担が大きく、精神的な葛藤を抱える調査員も少なくありません。今回は、70代男性の体験をもとに「現場の実情と課題」を整理します。
70代男性「軽い気持ちで受け後悔」
広島市に住む70代の男性は、町内会長から依頼を受け「年金生活の足しになれば」と調査員を引き受けました。担当区域は約80戸。最初は「なんとかなるだろう」と思っていましたが、次第に後悔の念が強くなったと語ります。
説明会と事前準備の壁
9月上旬に開かれた説明会では、映像や分厚い指導書を前に2時間以上の講習。細かな規定が多く、「覚えるだけでも気が重い」と感じました。
さらに、区域内の一軒一軒を訪ね、居住確認を行う作業も待っていました。毎日1万歩を超えるほど歩き回り、想像以上に体力を消耗。顔写真入りの調査員証を提げても、最初は住民から警戒されることもあり、「不審者扱いされないか心配だった」と振り返ります。
書類配布の苦労と仲間の支え
調査書類の封筒詰めも大きな負担でした。世帯ごとに異なる書類を番号と照合しながら仕分ける作業は、単純ながら神経を使います。「最初からまとめて配ってほしい」と思わず愚痴が出るほどでした。
ただ、この地域では調査員同士が集会所に集まり、情報交換や作業を一緒に進める機会がありました。
「この家は外国人世帯だから英語版を用意しよう」
「二世帯住宅だから2部必要だ」
といった住民ならではの知見を共有でき、少し安心できたといいます。
配布開始…想定外の難しさ
9月20日から始まった書類配布は、原則として世帯主に手渡しが基本です。ところが、昼間は不在家庭が多く、夜に訪ねると逆に怪しまれるという矛盾に直面しました。
「結局ポスト投函するしかないケースもあり、国の指導と現場の現実には大きなギャップがある」と男性は語ります。
また、インターホンを押しても出てもらえなかったり、無言でドアを閉められることもあり、「悪いことをしていないのに、後ろめたさを感じる瞬間があった」と振り返ります。
終わらない「催促業務」
書類を配布して終わりではなく、未回答世帯には再度訪問して回答をお願いする必要があります。協力的でない家庭に足を運ぶのは精神的に重く、近隣住民に居住の有無を確認する作業も気が引けるといいます。
「人の生活を詮索しているような気持ちになり、気が重い。やましいことはしていないのに後ろめたさがある」
と、葛藤を口にしました。
苦情対応に挟まれる現場
指導員のもとには「インターホンを押さなかった」との苦情と、「押されたら困る」との真逆の苦情が寄せられ、現場は板挟みに。調査員も「どう対応しても批判される」と悩むことが多いといいます。
男性の本音と今後への提言
男性は「次回も引き受けたいかと聞かれると迷う」と率直に語ります。一方で、地域を知らない外部の人が調査員を務めるのも不安だと感じ、複雑な思いを抱いています。
「国勢調査の制度は重要だが、現場の負担が大きすぎる。もっと調査員の声を聞き、現実に即した方法へ改善してほしい」
と訴えました。
まとめ:国勢調査の課題と改善の必要性
国勢調査は日本の将来の政策決定に欠かせない基盤ですが、調査員の高齢化や人手不足、住民の協力低下など課題が山積しています。現場の声を反映し、効率的かつ安全に運営できる仕組みが求められています。