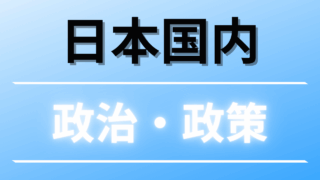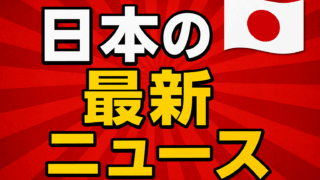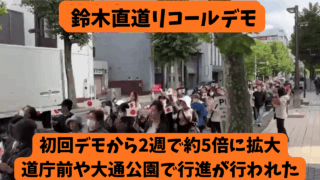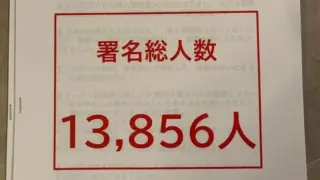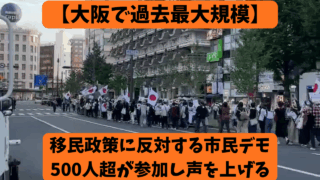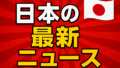2026年度から、**親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」が全国の自治体で導入されます。こども家庭庁は、制度の利用時間の上限を「月10時間」**とする方針を固めました。この記事では、制度の概要や注意点、保護者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 「こども誰でも通園制度」とは?
「こども誰でも通園制度」は、従来の保育園利用の条件である親の就労状況に関わらず、生後6カ月から3歳未満の子どもを施設に預けることができる制度です。従来は、働く親や就学中の親が対象でしたが、この制度によりすべての家庭が対象となります。
- 対象年齢:生後6カ月~3歳未満
- 利用条件:親の就労状況に関係なし
- 目的:子育て支援の公平性向上、家庭の負担軽減
2. 利用時間は「月10時間」が上限に
制度導入の背景には、全国的な保育士不足があります。そのため、政府は利用時間の上限を月10時間に設定しました。
- 25年度までに先行導入した自治体でも月10時間を上限
- 保護者からは「10時間では足りない」との声も
- 保育士や施設の負担を考慮した現実的な上限設定
また、26~27年度は人手不足や施設準備のための経過措置として、月3時間からの利用も認める予定です。
3. 制度導入にあたっての課題
制度の有識者会議では、以下のような課題が指摘されています。
- 保護者と信頼関係を築くのが難しい
- 子どもが安心できる場を確保しづらい
- 利用時間が短いため、家庭のニーズに対応できない場合もある
特に、月10時間という制限は、共働き家庭や長時間の保育を希望する家庭にとっては不十分と感じる可能性があります。
4. 保護者が知っておくべき注意点
この制度を利用する際に保護者が注意すべきポイントを整理します。
- 利用時間の制限
月10時間を超える利用は原則不可。必要に応じて、地域の保育施設や認可外保育の活用も検討する必要があります。 - 事前登録・予約の必要性
全国展開に伴い、自治体によって申請方法や受付状況が異なる可能性があります。事前確認が必須です。 - 施設の安全対策
少人数での利用が想定されるため、子どもが安心できる環境かどうかを確認することが重要です。 - 経過措置の活用
26~27年度は月3時間からの利用が可能なため、地域によっては段階的に制度に慣れることができます。
5. 制度活用の具体例
- 在宅ワーク中の親
月10時間程度、子どもを施設に預けることで作業時間を確保 - 育児リフレッシュ目的
家事や休息の時間を確保するために短時間利用 - 地域子育て支援の一環
子どもが同年代の子と交流できる場として活用
ただし、長時間の保育や就労サポートを希望する家庭にとっては補完的な制度として位置づける必要があります。
まとめポイント
- 「こども誰でも通園制度」は2026年度から全国展開、生後6カ月~3歳未満が対象
- 利用時間の上限は月10時間、人手不足地域では月3時間からの経過措置あり
- 保護者との信頼関係や子どもの安心環境確保が課題
- 利用にあたっては事前確認・安全面・家庭のニーズとの調整が重要
- 補完的な短時間保育としての活用が現実的
注意喚起
この制度は短時間利用を前提としているため、長時間の保育や就労サポートには十分ではありません。必要に応じて、地域の保育園や認可外施設、ベビーシッター制度などと併用することが推奨されます。また、申請方法や利用条件は自治体によって異なる可能性があるため、最新情報を必ず自治体ホームページで確認してください。
(出典:Yahoo!ニュース【独自】月10時間上限で全国展開へ 「誰でも通園」26年度から

【独自】月10時間上限で全国展開へ 「誰でも通園」26年度から(共同通信) - Yahoo!ニュース
こども家庭庁は、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を2026年度から全ての自治体で導入するのに当たり、利用時間の上限を「月10時間」とする方針を固めた。関係者が7日明らか