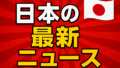今回のジジポリでは、JR東日本の地方路線赤字問題や、少子高齢化が鉄道経営に与える影響について解説していきます。
① 導入:地方鉄道の赤字が再び浮き彫りに
JR東日本は2024年度、地方路線36路線71区間の収支を公表しました。
結果は全区間で赤字、総額は約790億円に上りました。前年度より約33億円悪化しており、地域社会における鉄道維持の厳しさが改めて明らかになっています。
地方鉄道は、観光や通勤・通学に欠かせない重要なインフラですが、利用者の減少や運営コストの増加が深刻な課題となっています。
② 概要:収支の内訳と赤字の深刻さ
JR東日本の発表によると、開示された36路線71区間の運輸収入は約62億円。
一方、運行にかかる営業費用は約853億円にのぼり、差し引きで赤字総額は約790億円となりました。
特に深刻な区間は以下の通りです。
- 収支率最悪:陸羽東線(鳴子温泉―最上間)0.4%
→ 100円稼ぐのに2万2360円の費用が必要 - 赤字額最大:羽越線(村上―鶴岡間)約55億円
新型コロナ禍で先送りした線路の修繕費や災害復旧費も、赤字を拡大させる要因となっています。
③ 専門用語解説:収支率・輸送密度とは?
- 収支率:運輸収入を営業費用で割った割合。低いほど赤字が大きいことを意味する。
- 輸送密度:1キロあたりの1日平均乗客数。少ないと収入が少なく、赤字になりやすい。
JR東日本では、輸送密度2千人未満の区間を対象に赤字状況を集計しています。
④ 影響と今後の対応:地域交通の未来は?
赤字区間が多い背景には、以下の要因があります。
- 人口減少・少子高齢化 → 利用者減少
- 地方の移動需要低下 → 通勤・観光客の減少
- 運行コスト増加 → 線路保守・災害復旧費の増大
一方で、コロナ後に移動需要が回復した区間もあり、24区間で収支が改善しました。しかし長期的には、人口減少や高齢化によって再び赤字が拡大する可能性が高いとJR東日本は指摘しています。
地域の鉄道を維持するために、あなたならどのような対策が必要だと思いますか?
⑤ 読者への問いかけ
- 地方鉄道の赤字が続く中、地域住民としてどんな交通手段の改善策が考えられるでしょうか?
- 観光や通学需要を増やす取り組みで、鉄道収支は改善できると思いますか?
- 民間企業と自治体の連携による支援は必要でしょうか?
⑥ まとめポイント
- JR東日本の地方36路線71区間の赤字総額は約790億円
- 収入62億円に対し、費用は853億円で赤字が拡大
- 赤字の背景には人口減少・少子高齢化・運行コスト増がある
- コロナ後に一部収支改善もあるが、長期的な赤字懸念は依然として大きい
- 地域交通維持には、自治体・企業・住民の協力が不可欠
(出典:Yahoo!ニュース「JR東日本、地方36路線で赤字 24年度、総額790億円」

JR東日本、地方36路線で赤字 24年度、総額790億円(共同通信) - Yahoo!ニュース
JR東日本は27日、利用者が少ない地方路線の2024年度の収支を公表した。開示した36路線71区間の全てで赤字だった。開示した区間の運輸収入は約62億円で、運行にかかった営業費用は約853億円だっ