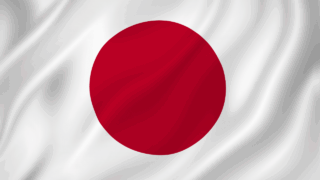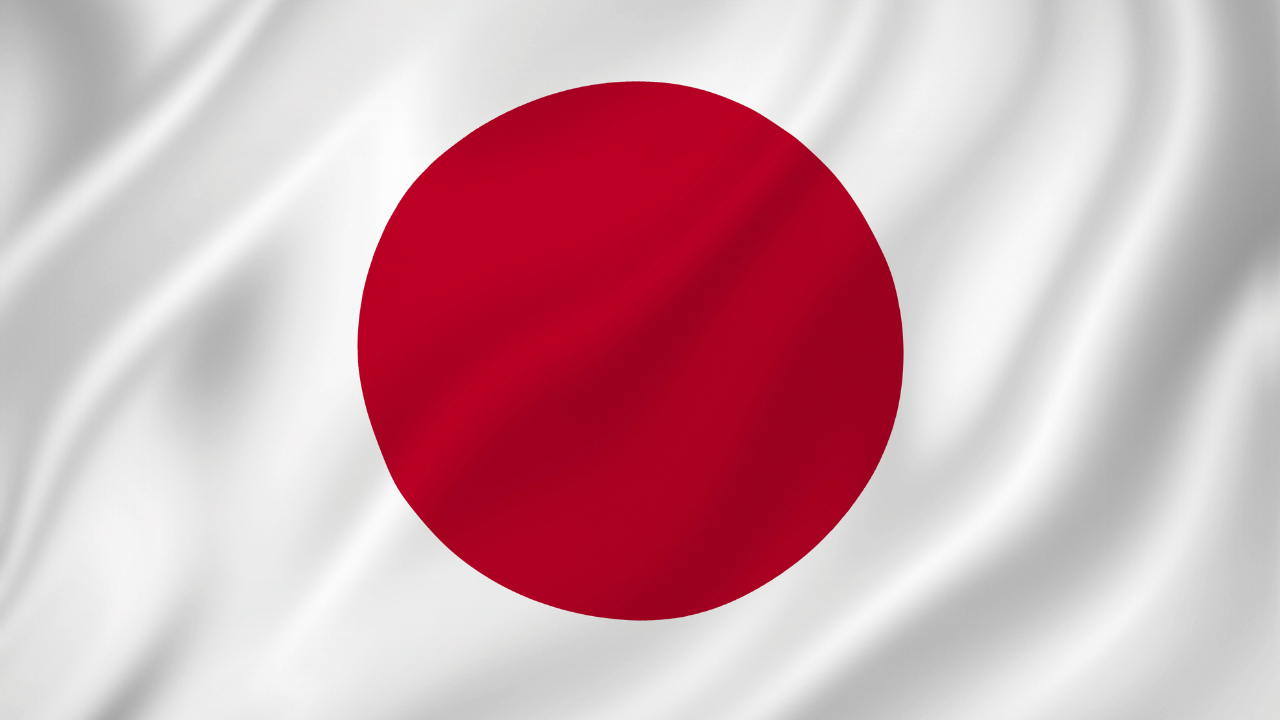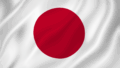日本政府が国際機関に拠出している「任意拠出金」の運用について、会計検査院が調査を行った結果、追加拠出分の約3割にあたる資金で、事業に使う見込みのない余剰金の有無が把握されていなかったことが明らかになりました。会計検査院は26日、公表した報告書で「余剰資金の有無を確認することは、必要以上の拠出を避け、国際機関における資金の有効活用を促すうえで重要である」と指摘しています。
任意拠出金の概要
国際機関への拠出金は、国連の分担金などの義務的拠出金と、政府の裁量で支援する任意拠出金に分けられます。任意拠出金は、日本の国際貢献や国益確保のため、有益で支援すべき事業を対象として拠出されます。
2018~2023年度における国際機関への総拠出額は5兆237億円で、そのうち任意拠出金は3兆292億円に上ります。会計検査院は、この期間の追加拠出分384件を対象に精査しました。
調査結果
調査の結果、約3割に当たる123件について、所管する15府省庁が余剰資金の有無や繰越金を十分に把握していなかったことが判明しました。
具体例として、情報通信技術(ICT)発展を目的としたASEAN基金では、総務省は2009年度から任意拠出金を提供。2018年度には約3713万円の繰越金が存在していたにもかかわらず、余剰金の確認を行わず、18~23年度に計約6850万円を追加拠出。結果として繰越金は約8155万円まで膨らみました。
総務省は検査院に対し、「事業計画を確認したうえで追加拠出したが、ASEAN各国からの要望も考慮し、余剰資金を確認せずに毎年度同額を拠出した」と説明しています。
一方で、一部の府省庁は「国際機関の判断を尊重しつつ、日本の国際的プレゼンスを維持するためには、繰越金や余剰資金の状況に左右されず拠出する必要がある」との理由で、余剰金確認の意義が乏しいと回答していました。
まとめ・ポイント
- 任意拠出金の3割で余剰金未把握
- 会計検査院の調査で、追加拠出分の123件に余剰金確認がされていないことが判明
- 国際機関への資金拠出の透明性の課題
- 必要以上の拠出を避け、資金の有効活用を促すために余剰金把握が重要
- 具体例:ASEAN基金
- 繰越金の存在を確認せず追加拠出、結果として基金残高が膨張
- 各府省庁の対応方針の違い
- 一部は余剰金確認の重要性を認めつつも、国際的プレゼンス維持のため拠出継続を重視
- 今後の課題
- 任意拠出金の運用において、事前の余剰金確認や将来の支出見込みの検討が求められる
この調査は、日本政府の国際貢献のための資金拠出において、透明性と効率性を確保する必要性を改めて浮き彫りにした事例となっています。