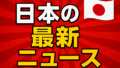今回のジジポリでは、急速に進む人口減少と少子化対策の課題について解説していきます。
① 導入:深刻化する人口危機、日本の未来に影響
日本では今、かつてないスピードで人口が減少しています。2025年現在、総人口はおよそ1億2400万人。しかし、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2070年には8700万人まで減る見込みです。
つまり、45年で3700万人が減少するという深刻な状況です。
物価高や長時間労働、結婚・出産への不安が広がる中、「2人目は難しい」と感じる家庭が増えています。あなたの周りでも、同じように“子どもを持つ決断”に悩む人はいませんか?
② 概要:出生数は過去最少、婚姻数も減少
- 日本の出生数は68万人余り(2024年)で、戦後のピーク時(1949年)の約4分の1に落ち込みました。
- **合計特殊出生率(女性が生涯に産む子どもの平均数)**は1.15と過去最低。
- 婚姻数も50万組を下回り、少子化のスピードは国の想定を15年も上回っています。
一方で政府は、少子化対策として児童手当の拡充や育休給付の見直しを進めています。
例えば、2024年からは高校生までが児童手当の対象になり、第3子以降は月3万円が支給されるようになりました。
また、共働き夫婦が14日以上の育休を取ると、手取り収入が育休前と同水準になる制度も導入されています。
しかし、「制度が増えても現場の働き方は変わらない」との声が多く、効果は限定的です。
③ 専門用語解説:合計特殊出生率とは?
合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)とは、
「1人の女性が一生のうちに産む平均の子どもの数」を示す指標です。
日本では2.07以上であれば人口が維持できるとされますが、現状は1.15と大きく下回っています。
このままでは、働き手や社会保障を支える人口が急減し、経済や地域社会の維持が困難になると懸念されています。
④ 影響と今後の対応:北欧に学ぶ「社会全体で育てる」仕組み
スウェーデンなど北欧諸国では、国全体で子育てを支える仕組みが整っています。
例えば:
- 父親の育休取得率が高く、家庭と仕事の両立が当たり前
- 小学校から大学まで学費が無償
- 経済的に子どもを育てやすい社会制度
これにより一時期出生率を1.9台まで回復させた実績があります。
一方、日本では「長時間労働」「保育園の不足」「地方での雇用難」が課題として残っています。
制度面の支援だけでなく、働き方や家族観そのものを変える社会的意識改革が必要です。
あなたは、どんな支援があれば「子どもをもう一人」と思えますか?
⑤ 読者への問いかけ
- 仕事と家庭、どちらかを諦めなければならない現状をどう変えるべきか?
- 国の政策だけでなく、地域や企業ができる支援とは?
- 「子どもを持つ幸せ」と「経済的な現実」、どちらを優先すべきか?
まとめポイント
- 日本の人口は2070年に8700万人まで減少する見込み
- 出生率は過去最低の1.15、婚姻数も90年ぶりの低水準
- 政府は児童手当や育休制度を拡充中だが、働き方改革が進まないのが課題
- 北欧諸国は「社会全体で子育てを支える」仕組みで一時的に出生率を回復
- 日本も「制度+意識改革」で次世代を支える社会への転換が急務
(出典:Yahoo!ニュース「2人目は難しいかもね」物価高・長時間労働が出産の壁、深刻化する急速な人口減少