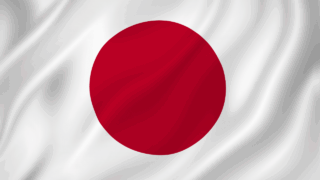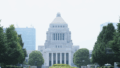政府は、日本社会への影響を踏まえて外国人受け入れ政策の抜本的な見直しに動き出しました。入管庁や有識者会議で議論を重ね、関係閣僚会議で新方針を決定する見通しです。目的は、社会保障や賃金、治安への影響を精査したうえで、必要に応じて受け入れに一定の制限を設けることにあります。
鈴木馨祐法相の報告
入管庁を所管する鈴木馨祐法相は、29日の閣議後会見で、検討すべき論点をまとめた報告書を公表しました。庁内にはプロジェクトチームが設置され、「可能な限り速やかに検討を進める」と説明。
報告書では、これまでの外国人政策について「対症療法的で、統一方針がない」と指摘し、将来的な外国人比率の増加を見据えて、多角的に検討する必要性を示しています。
外国人受け入れの現状と将来
総務省の人口推計(2025年3月確定値)によると、国内の外国人人口は356万5千人で全体の2.9%。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、外国人比率が1割を超えるのは2070年とされていますが、報告書ではより早期に到来する可能性があると警鐘を鳴らしています。
このため政府は、受け入れ規模に応じた経済成長シナリオを作成し、以下の分野への影響を調査することを検討しています。
- 財政
- 社会保障
- 賃金
- 教育
- 治安
さらに、国と地方自治体の役割を整理し、社会との摩擦を和らげるための社会統合プログラムの策定も課題として挙げています。
受け入れ制限の検討
報告書では、「特定技能」や「育成就労(27年度から)」以外の在留資格で滞在する外国人について、受け入れ上限を設ける可能性を示しています。摩擦が社会の許容度を超える場合は、時限的に受け入れ制限を実施する方法も検討されるとのことです。
外国人比率が高い市区町村
国内では、一部の市区町村で外国人比率が10%を超えています。2025年1月1日現在、上位は以下の通りです。
- 北海道占冠村(36.6%)
- 北海道赤井川村(35.3%)
- 大阪市生野区(23.3%)
- 群馬県大泉町(21.3%)
- 北海道倶知安町(21.2%)
その他、大阪市浪速区(16.6%)、東京都新宿区(13.6%)、横浜市中区(12.0%)、大阪市中央区(10.4%)など、多くの都市で外国人比率が10%を超えています。
まとめとポイント
- 政府は外国人受け入れ政策の抜本見直しに着手。社会保障、賃金、治安などへの影響を調査し、必要に応じて受け入れ制限を検討する。
- 報告書ではこれまでの政策の統一方針の欠如を指摘し、将来的な外国人比率の増加に備えた長期的なシナリオを策定する方針。
- 国と地方自治体の役割を整理し、社会統合プログラムを整備して摩擦を最小化する計画。
- 特定技能や育成就労以外の在留資格での滞在者については、上限や時限的制限の可能性も議論されている。
- 国内では一部市区町村で外国人比率が10%を超えており、地域ごとの状況を踏まえた政策運営が求められる。