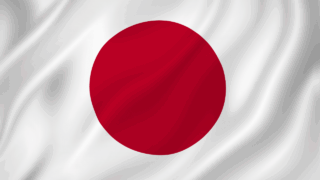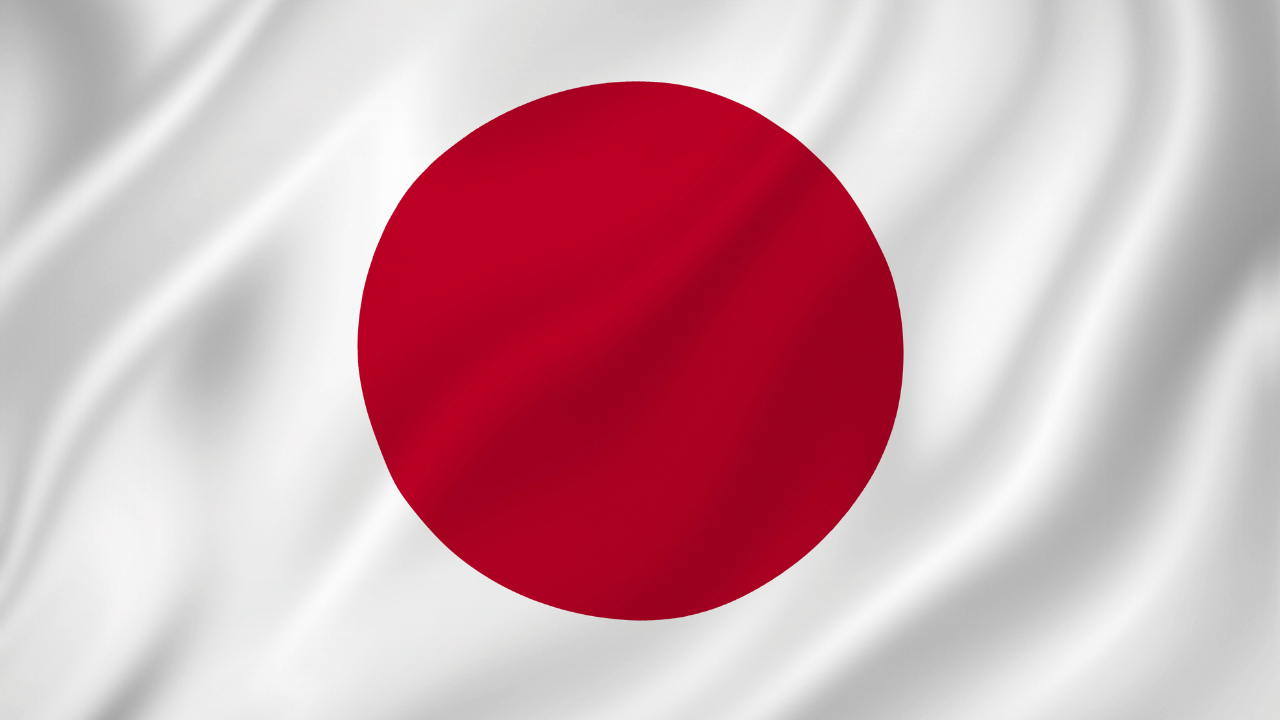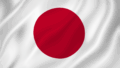2020年度に始まった「大学授業料の無償化(高等教育の修学支援新制度)」は、国が大学や短大、高専などに通う学生の授業料・入学金を支援する仕組みです。少子化対策や教育格差の是正を目的として導入され、今年度は制度がさらに拡充されました。特に「多子世帯(子どもが3人以上いる家庭)」に対しては、親の所得制限が撤廃され、利用できる世帯が一気に増えたことが特徴です。
実際、2023年度の対象者は約34万人でしたが、今年度は推計で約84万人に拡大。国公立大学では入学金28万円と授業料54万円が全額免除、私立大学でも入学金26万円・授業料70万円までが免除されるため、家計への負担軽減効果は大きく、多くの家庭から歓迎の声が上がっています。
それでも救われない「3浪以上」の学生たち
一方で、この制度には見落とされがちな“落とし穴”があります。
それが「3浪以上して入学した学生は対象外」というルールです。
例えば、ある関西在住の女性は3人の大学生の子どもを持っています。娘2人は制度の支援を受けられましたが、医療系学部に4浪して入学した長男は申請が却下されました。理由を調べると、日本学生支援機構の規定に「高校卒業の翌年度の末日から大学入学日まで2年を経過していないこと」という条件が明記されていたのです。つまり、高卒から3年以上たって大学に入学した場合、たとえ家庭環境や本人の努力に関係なく支援を受けられない仕組みになっています。
なぜ「3浪の壁」があるのか?
文部科学省の担当者はその理由について「高校卒業後に専門学校へ進学する場合、2年で社会に出るケースが多いことを参考にした」と説明しています。要するに、就職や扶養関係の区切りを基準にした制度設計だというのです。
また、財政的な側面も大きな要因です。統計上、3浪以上して大学に進学する学生は全体の1%程度、約6000人と推計されます。仮にこの全員を国公立大学生として無償化の対象にすると、授業料だけで年間約32億円超の予算が追加で必要になります。限られた財源の中で線引きをせざるを得なかった、というのが文科省の立場です。
「画一的な進学モデルに縛られるべきではない」との指摘も
しかし、教育の専門家からは制度のあり方に疑問の声も出ています。
進路アドバイザーの倉部史記氏は、この「3年の壁」について懐疑的な立場を示しています。
「高校を出てすぐ大学に入るという画一的な進学モデルを前提とした制度設計になっており、柔軟性に欠ける。浪人や回り道を経て大学に挑戦する若者にとって、制度から排除されることは挑戦の機会を奪う恐れがある」と指摘しています。
実際、医学部や難関学部を目指して複数年浪人する学生は少なくなく、病気や家庭の事情で進学が遅れるケースもあります。そうした背景を考慮せずに一律で支援対象から外すのは、公平性を欠くとの批判も根強いのです。
今後の課題―「挑戦できる教育環境」をどう整えるか
大学授業料の無償化制度は、多くの家庭にとってありがたい支援である一方、「3浪以上は対象外」という条件は見直しの余地があるかもしれません。教育は本来、年齢や経歴を問わず誰にでも開かれているべきものです。少子化が進む今だからこそ、多様なキャリアや学び直しを支える制度設計が求められているのではないでしょうか。
まとめのポイント
- 大学授業料無償化制度は少子化対策として拡充され、対象者は大幅に増加。
- しかし「高校卒業から3年以上経過して入学した学生」は支援対象外。
- 文科省は「専門学校卒業=社会進出」や予算制約を理由に説明。
- 3浪以上の学生は全体の1%程度だが、挑戦の機会を奪う懸念も指摘される。
- 今後は「年齢や経歴にとらわれない教育支援」のあり方が課題。