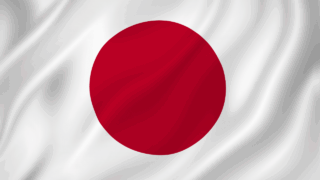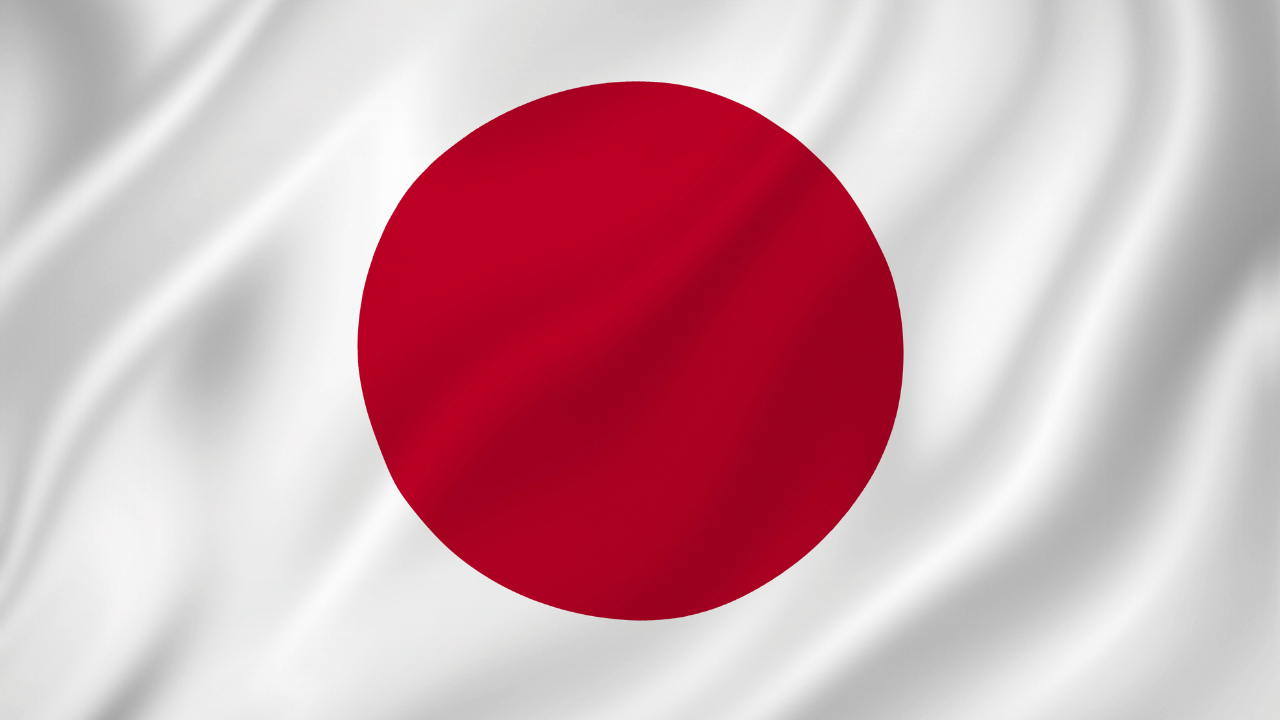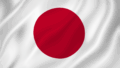マクドナルドに殺到した転売ヤー
2025年夏、日本マクドナルドはハッピーセットに「ポケモンカード」を付けるキャンペーンを実施しました。子ども向け商品であるにもかかわらず、希少性の高いカードが目当ての転売ヤーが殺到。店舗には長蛇の列ができ、本来ターゲットである子ども連れの家族が購入できない事態となりました。
さらに、食事そのものには興味がなく、商品が店内に放置されるケースも相次ぎ、SNSでは批判が噴出。ブランドイメージの低下にもつながりました。
マクドナルドは当初「1人5セットまで」と購入制限を設けていましたが、並び直しや複数店舗を回る方法で簡単に突破されてしまいました。モバイルオーダーの制限を行わなかったことも混乱を拡大させ、最終的にわずか1日で配布は終了しました。
ポケモンカード人気と「大人需要」
背景にはポケモンカードの異常な人気があります。コロナ禍以降の巣ごもり需要で市場は急拡大し、2024年度には国内市場規模が約3000億円に到達。すでに玩具の枠を超え、投資やコレクションの対象となっています。
希少カードは100万円単位で取引されることもあり、犯罪組織のマネーロンダリングに利用される事例も報告されています。こうした状況を踏まえると、子ども向け商品にカードをおまけとして付けること自体が転売ヤーを呼び込む要因だったといえるでしょう。
吉野家が採用した「時間差戦略」
一方、吉野家は「おまけ商法」において異なるアプローチを取りました。2024年に実施した「カービィ盛」キャンペーンでは、カービィのフィギュアが付属し一時は転売ヤーが殺到しました。しかし、その後の第3弾では対策を強化。
主な特徴
- 牛丼の購入額に応じてポイントを付与
- 一定ポイントを貯めた後に景品を申し込む方式
- 景品は即時ではなく半年後に発送
この「時間差戦略」によって、転売ヤーにとってのリスクが高まりました。半年後にフィギュアの人気が継続している保証はなく、大量購入しても利益を得られるかは不透明です。結果的に、SNSでは「吉野家の転売ヤー対策は巧妙」と評価され、マクドナルドとの対比で好意的に受け止められました。
Nintendo Switch2の「抽選と価格差」戦略
転売ヤー対策の事例として、任天堂の「Nintendo Switch2」も注目されています。日本語版を低価格に、海外向け多言語版を高価格に設定することで海外転売のうまみを削減。
さらに、応募条件として「50時間以上のプレイ実績」を求める抽選方式を採用し、転売目的で新規アカウントを作って応募することを困難にしました。消費者に「いつか正規価格で買える」という安心感を与えることで、高額転売を抑止しています。
転売ヤー対策に必要な発想
単なる購入制限や本人確認だけでは、転売ヤーを完全に防ぐことはできません。複数人を動員して並び直す、複数アカウントを使うといった抜け道が常に存在するからです。
そのため効果的な方法は、吉野家の「時間差提供」や任天堂の「抽選・条件付き販売」のように、転売ヤーにとって“在庫リスク”を増大させる仕組みを導入することだといえます。
加えて、企業側が転売ヤーでも「売れれば成功」と考えるのではなく、本来の顧客層に商品を届ける姿勢を持たなければブランド価値の毀損につながるでしょう。
まとめのポイント
- マクドナルドは購入制限の甘さから転売ヤーを招き、ブランドイメージ低下を招いた
- 吉野家は「時間差提供」で転売ヤーの利益を抑止し、消費者から好評価を得た
- 任天堂は「抽選方式」「価格差」「条件付き応募」で転売対策を徹底
- 転売ヤー対策には「購入制限」だけでなく、リスクを高める仕組み作りが必要
- 企業は短期的利益より「顧客満足度とブランド保護」を優先すべき