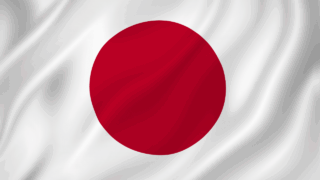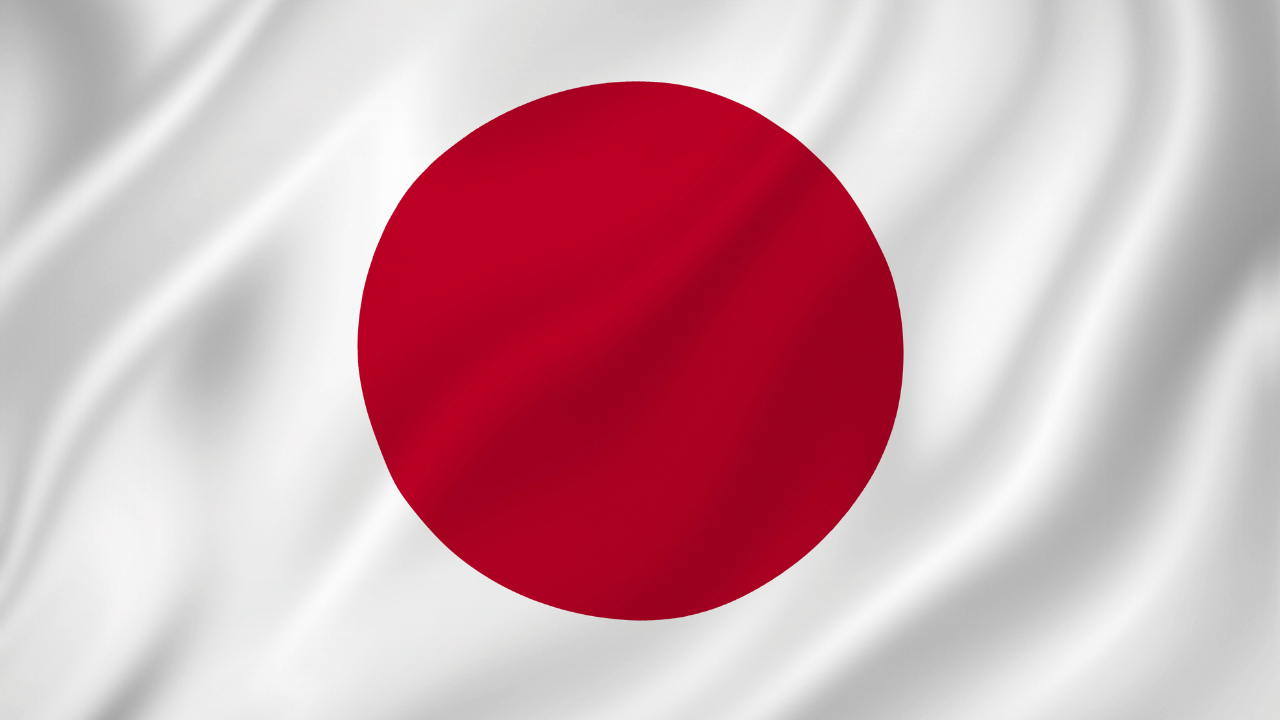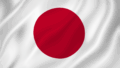近年、学校や部活動での教師・顧問による「体罰」の問題が注目される機会が増えています。特に、昭和時代に見られたいわゆる「熱血指導」が、現代の教育現場では通用しなくなってきていることが指摘されています。
最近の事例では、高校の女子バスケットボール部の顧問が、生徒たちに「挨拶ができていない」という理由で、7kmもの距離を歩かせたとして問題となり、学校側が生徒や保護者に謝罪するという出来事もありました。このような過度な身体的負担を伴う指導は、現代の教育現場では体罰と見なされる可能性があります。
弁護士ドットコムには、生徒から「雑巾掛け」に関する相談も寄せられています。例えば、授業中の忘れ物やテストの点数が基準に達しない場合に、教室の廊下やフロアで長距離の雑巾掛けを命じられることがあります。高校生の場合でも、延べ1km以上の雑巾掛けは身体的負担が大きく、教育的配慮の範囲を超える場合には体罰に該当する可能性があります。
学校教育法第11条では、教員は教育上必要な場合に「懲戒」を行うことは認められていますが、「体罰」は禁止されています。懲戒であっても、教育的配慮がなされ、児童・生徒に過度な苦痛を与えないことが求められます。過去には、中学生に廊下を100往復雑巾掛けさせたり、小学生に便器周りの清掃を素手で行わせたりした事例が報告され、これらは「懲戒」の範囲を超える行為として体罰と判断されました。
文部科学省のガイドラインでも、懲戒行為が体罰にあたるかどうかは、教員や生徒・保護者の主観だけで判断するのではなく、児童・生徒の年齢、健康状態、心身の発達状況、行為が行われた時間や場所、懲戒の態様などを総合的に評価して判断すべきとされています。
短時間で行う教室内や廊下の雑巾掛けなど、心身に過度な負担をかけない範囲であれば、教育的目的に沿った「懲戒」として許容される場合もあります。しかし、長距離や長時間の雑巾掛けは身体的苦痛を伴い、教育的配慮に欠けるため「体罰」と見なされる可能性が高くなります。
近年では、ウサギ跳びや長時間ランニング、水を飲ませないトレーニング、授業中の長時間正座や直立姿勢の強制なども体罰と判断されるようになってきています。つまり、従来は熱血指導の一環として許容されていた行為も、現在では体罰に分類されるケースが増加しているのです。
まとめポイント
- 熱血指導は現代では通用しない
昭和の体罰的指導は現在の教育基準では認められない。 - 雑巾掛けも体罰になる可能性
長距離・長時間の雑巾掛けは、教育的配慮を超えた場合に体罰と判断される。 - 教育的配慮が重要
年齢・健康・行為の内容・場所・時間を総合的に考え、過度な身体的負担は避けるべき。 - ガイドラインに従った懲戒を
児童・生徒への懲戒行為は、客観的に適切性を評価し、教育的目的を明確にすることが必要。