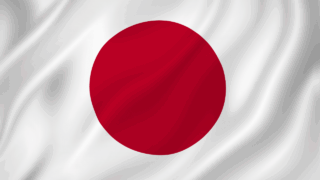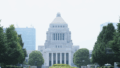10月4日に投開票を控える自民党総裁選では、物価高対策が重要な論点のひとつとなっています。2025年7月の参議院選挙では、与党が一律現金給付を訴えましたが、選挙結果は与党の過半数割れにつながり、政策評価が振るわなかった経緯があります。その後、政策対応が遅れたこともあり、総裁選では各候補とも現金給付の訴えを事実上封印し、所得減税や低所得者向け支援策を前面に打ち出す形となっています。しかし、総裁選の実施そのものが「政治空白」を生み、庶民生活への迅速な対応が遅れることへの批判も出ています。
柏市の商店街で見える家計圧迫の現実
千葉県柏市のJR柏駅前、柏二番街商店会にある食品スーパーでは、日常的に主婦や学生が買い物に訪れています。68歳のパート主婦は、豚肉や野菜、調味料の高騰を嘆き、「お米がムチャクチャ高い。野菜も本当に異常」と語ります。夫と孫2人と同居しており、孫が大学生と高校生のため食費がかさむとのことです。日々の節約術としては、スーパーごとに価格を確認し、安いものを見つけては購入する方法を採っています。自身はお菓子やおかずを我慢することもあり、家族の生活を守るために工夫を重ねています。
20歳の大学生男性も、生活費はアルバイト収入に依存しており、菓子パンや作り置きのパスタだけでしのぐ日もあります。その他の買い物客も、ふるさと納税で日用品を確保したり、複数のスーパーを使い分けたりと、涙ぐましい工夫を続けています。
食料品以外にも広がる物価高
物価高は食料品にとどまらず、幅広い品目に及んでいます。帝国データバンクによると、2025年に値上げを予定している飲食料品は11月までで約2万品目に上り、前年実績(1万2520品目)を大きく上回ります。特にコメは、政府備蓄米の放出により一時的に価格が落ち着いたものの、新米が出回る9月以降、スーパーでの平均価格は5キロあたり4000円台を突破しています。
さらに、ガソリン価格の高止まりや人件費高騰の影響で地方の公共交通料金や携帯電話料金も上昇。中小企業だけでなく、高収益の大手企業でも料金値上げが相次ぎ、消費者の生活を圧迫しています。
総裁選における物価高対策の現状
総裁選の候補者たちは、物価高対策として所得税減税や低所得者向け支援策を掲げています。参院選で公約に掲げられた現金給付は評価されず、与党候補は事実上封印。また、野党が訴えた消費税減税についても、党内で慎重姿勢が強く、声高に主張する候補はいません。結果として、具体的な減税額や給付内容は曖昧で、政策は「生煮え」の印象を与えています。
衆参両院で少数与党となる中、新総裁が打ち出す経済政策は、野党の協力抜きでは国会で成立しません。立憲民主党は、参院選後の2カ月間の政策停滞を批判し、迅速な結論を求めています。国民民主党も、年収103万円の壁引き上げやガソリン税暫定税率廃止など、迅速な物価対策を実施するようけん制しています。
日銀のジレンマと庶民生活
金融政策を担当する日本銀行も、物価高への対応で難しい判断を迫られています。円安の長期化が輸入品価格を押し上げる一方、円高による輸出企業の収益悪化や景気冷却のリスクも存在します。日銀は2%の物価上昇目標を掲げていますが、急激な物価高に賃金上昇が追いつかず、実質賃金はマイナス圏で推移しています。柏市の82歳主婦は「国の政策は全て時間がかかる。今苦しんでいるのだから、今助けてほしいのに」と話し、庶民の生活実感を代弁しています。
中立的視点での考察
今回の総裁選を巡る物価高対策の議論は、党内政治と庶民生活の間にあるギャップを浮き彫りにしています。政策の遅れや具体性の乏しさは、生活に直接影響を受ける市民の不満を招きます。一方で、現金給付や消費税減税には財政面の制約や党内調整の難しさがあり、政策実現には限界があることも事実です。中立的には、政治家と中央銀行双方が即効性のある生活支援策と、財政・金融の持続可能性のバランスを取ることが重要だと言えます。
まとめのポイント
- 自民党総裁選2025では、物価高対策が主要テーマだが、現金給付は事実上封印され、所得減税などに重点。
- 庶民生活は依然として圧迫され、食料品や日用品、交通費や通信費の高騰が家計に影響。
- 総裁選の政局中心の議論が「政治空白」となり、迅速な政策対応が求められる。
- 日銀も対応にジレンマを抱え、庶民の実質賃金低下が長期化。政策の即効性と持続可能性のバランスが課題。