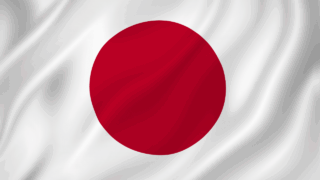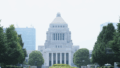自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農相をめぐり、9月26日にX(旧Twitter)での言及が急増したことが30日、報じられた。これは、陣営内でのインターネット配信動画へのコメント投稿要請に対して小泉氏が陳謝した日に重なる。投稿内容の多くは、広告表示なしで商品などを宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」に近い行為としての批判を含んでいた。
調査期間中のポスト総数では、26日まで高市早苗前経済安全保障担当相が最多だったが、27日には小泉氏が逆転。SNS上での反応の急増は、政治家や陣営によるネット上の情報操作のリスクや、危機管理の重要性を改めて示す結果となった。
SNS分析と注目ポイント
共同通信は、NTTデータの交流サイト分析サービス「なずきのおと」を用いて、8日から27日までの20日間、総裁選と候補者名が記された投稿を抽出。批判的な投稿も含まれるため、言及数がそのまま支持動向を表すものではないと注意を促している。
期間中、小泉氏に関するポストは、25日までは1日最大約10万件だったが、26日には28万件、27日には23万件と、2位の高市氏の約2倍に急伸した。これは、陣営のネット対応と候補者自身のコメントがSNSで大きく注目された結果と考えられる。
ステマ疑惑と政治家の責任
今回の急増は、政治家や陣営のSNS運用における透明性の重要性を浮き彫りにした。特に広告やプロモーション投稿の表示義務や、情報操作のリスクに対する危機管理が不十分である場合、候補者自身の信頼性にも影響を与えかねない。また、SNSでの反応はリアルタイムで拡散されるため、発言内容や陣営の対応の是非が瞬時に世論に反映されることも示されている。
中立的視点での考察
今回の事例から、以下の点が注目される。
- SNS上での言及数の急増は、支持動向を示すものではなく、あくまで話題性の指標である。
- 政治家や陣営は、SNS投稿における透明性と情報管理を徹底する必要がある。
- ネット上での炎上リスクや批判への対応は、政治家の信頼性に直結する。
総裁選を控えた現状では、SNSの反応が政策議論や支持動向の一部として注目される一方で、候補者はネット上の批判や誤解に惑わされず、透明かつ責任ある対応を続けることが求められる。
まとめポイント
- 小泉進次郎氏の陳謝により、9月26日から27日にかけてXでの言及が急増。ポスト数は高市早苗氏を上回った。
- 急増の背景には、陣営のコメント投稿要請とステルスマーケティング疑惑への批判がある。
- SNSでの言及数は話題性の指標であり、支持率の直接的な反映ではない。
- 政治家はSNS運用における透明性と危機管理を徹底する必要がある。
- ネット上での批判や炎上リスクへの対応は、候補者の信頼性や政策実現能力に影響する。