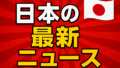今回のジジポリでは、埼玉県三郷市で起きた小学生4人ひき逃げ事件の初公判と、外国人被告の発言が社会に与えた影響について解説していきます。
① 導入:社会を揺るがす「外国人による飲酒ひき逃げ事件」
2025年5月に埼玉県三郷市で発生した小学生4人のひき逃げ事件が、再び注目を集めています。
加害者である**中国籍の鄧洪鵬(とう・こうほう)被告(43)**が、初公判で起訴内容を認めたうえ、事件後に「日本語が分からないと言えばいい」と話していたことが明らかになりました。
この発言はSNSを中心に波紋を呼び、
「逃げる前提の発言ではないか」「外国人による法の軽視では?」といった批判が広がっています。
交通事故は一瞬で人生を変える事件です。
飲酒運転と逃走、そして“言葉の壁”を悪用するような態度——
果たして日本社会はどう受け止めるべきなのでしょうか?
② 概要:飲酒運転→ひき逃げ→隠蔽 ドライブレコーダーに一部始終
検察の冒頭陳述によると、鄧被告は事件当日、
友人と中華料理店で生ビールを5杯飲酒した後、車を運転。
帰宅途中の小学生の男子児童4人をはね、ケガを負わせたにもかかわらず、そのまま現場から逃走しました。
ドライブレコーダーには以下の音声が残されていたといいます。
- 同乗者:「止まって、警察を呼ぼう」
- 鄧被告:「行こう、行こう」「日本語が分からないと言えばいい」「まずは車を隠す」
これらの発言が飲酒運転と逃走の故意(わざと行った)を裏付ける証拠として提出されています。
被告は初公判で「間違いありません」と認め、罪状を争わない姿勢を示しました。
③ 専門用語解説:ひき逃げと飲酒運転の違い
事件を正しく理解するために、2つの用語を整理しておきましょう。
- 飲酒運転:アルコールを摂取した状態で車を運転する行為。基準値を超えると道路交通法違反となり、懲役や罰金の対象になります。
- ひき逃げ(救護義務違反):交通事故の被害者を救助せずに逃げること。刑法では10年以下の懲役など、極めて重い罪に問われます。
つまり今回の事件は「飲酒運転」と「ひき逃げ」の二重の重大違反ということになります。
では、なぜこのような事件が繰り返されてしまうのでしょうか?
④ 影響と今後の対応:外国人ドライバーへの管理と再発防止策
日本国内では、在留外国人の自動車利用が増える一方で、
交通ルールや法制度の理解不足が指摘されています。
ただし今回の事件では、単なる「文化や言葉の違い」ではなく、
意図的に法を逃れようとした発言が問題の核心です。
▶ 社会的な影響
- SNSでは「言葉を盾に逃げるのは卑怯」「被害者の子どもたちがかわいそう」と怒りの声が殺到。
- 一方で「一部の行為で外国人全体を偏見の目で見るべきではない」という冷静な意見も。
▶ 今後の課題
- 外国人ドライバーへの交通法教育の強化
- 免許交付時の法的責任・倫理教育の義務化
- 交通事故時の逃走に対する刑罰のさらなる厳罰化
被害者の小学生4人はいずれも命に別状はありませんでしたが、心の傷は深く、地域の保護者からも「再発防止を求める声」が高まっています。
⑤ 読者への問いかけ:法律を“知らないふり”で逃げる社会を許せるか?
「日本語が分からない」と言えば罪を逃れられる——。
そんな考え方を、私たちは社会としてどう受け止めるべきでしょうか?
言葉や国籍に関係なく、日本に住む以上は同じ法の下で責任を負うことが求められます。
この事件は、単なる交通事故ではなく、日本社会の“公平さ”を問う事件でもあります。
🟫 まとめポイント
- 埼玉県三郷市で小学生4人が車にはねられ、中国人被告がひき逃げ容疑で起訴
- 被告は飲酒運転を認め、事故後「日本語が分からない」と発言
- ドライブレコーダーの音声が重要な証拠に
- 外国人ドライバーへの法教育強化と厳罰化の議論が進む見通し
- 社会として「逃げ得」を許さない姿勢が問われている
(出典:Yahoo!ニュース「小学生4人ひき逃げ直後に「日本語が分からないと言えばよい」発言か…中国人被告が初公判で起訴内容認める 飲酒してひき逃げした罪で 埼玉・三郷市」