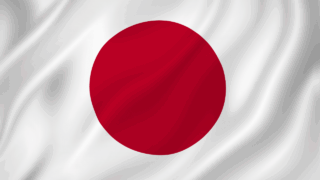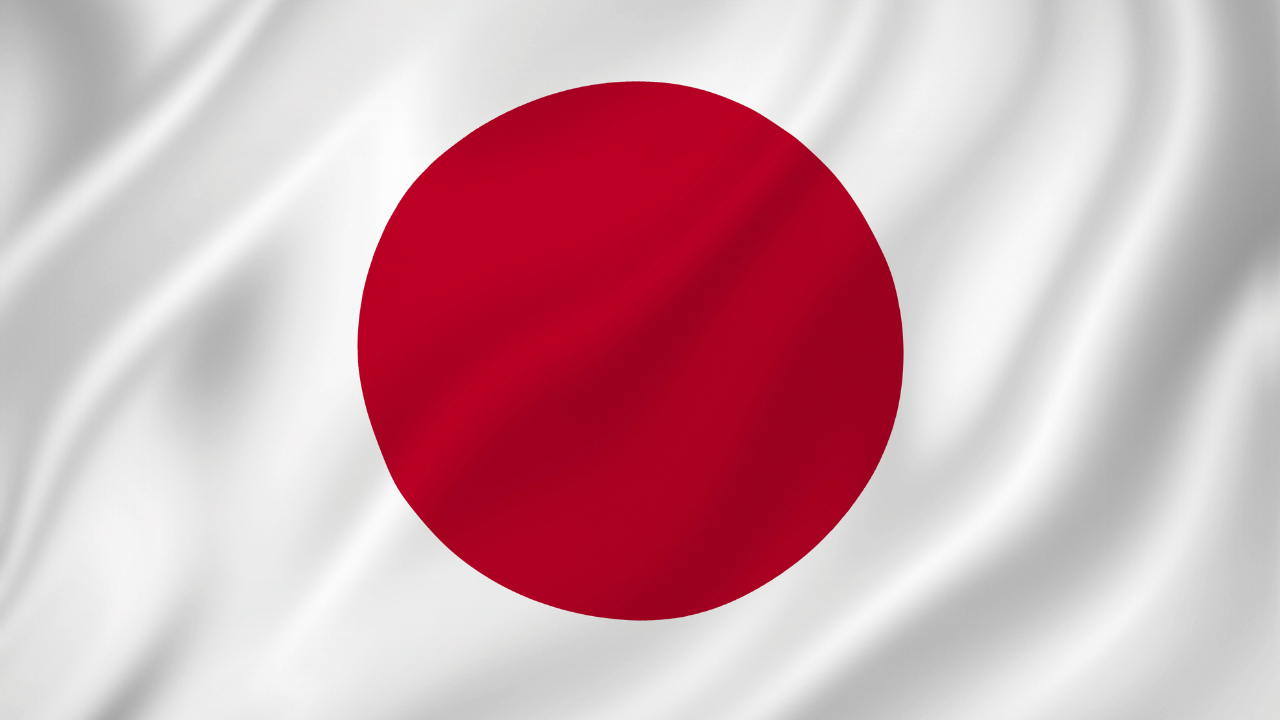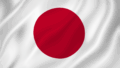交通事故で人命が失われるケースでは、運転者の行為が「不注意による過失」なのか、それとも「危険で悪質な運転」によるものなのかを区別することが重要です。この判断に用いられるのが、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪です。しかし、実際の運用においては両者の線引きがあいまいであるとの指摘が多く、事故遺族からは法制度の改善を求める声が上がっていました。
この問題を受け、2025年9月29日、法務大臣の諮問機関である審議会の部会において、危険運転致死傷罪の数値基準を盛り込んだたたき台が初めて示されました。これにより、「どの程度の速度超過や飲酒量で危険運転と認定されるか」がより明確化される方向です。
高速度による事故の事例と遺族の声
2021年2月、大分市で発生した事故は、危険運転致死罪の適用の難しさを象徴しています。19歳の男性が法定速度60キロの市道で時速194キロで走行し、右折してきた車と衝突。被害者である小柳憲さん(当時50歳)が死亡しました。
事故から1年5カ月後、弟を亡くした長文恵さんは、以下のように当時の心境を振り返ります。
「常軌を逸した法定速度の約3倍での事故だったにもかかわらず、当初は過失運転致死罪での起訴。なかなか危険運転と認めてもらえないことに疑問を感じました」
1審の大分地裁は、ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで事故を起こす危険性があるとして、危険運転致死罪を認定。懲役8年の判決が言い渡されました。しかし、控訴審でも「進行を制御することが困難な高速度」にあたるかが争点となっています。
法律上の課題と数値基準の必要性
現行法では、法定速度をどの程度超えれば危険運転と判断されるかという具体的な数値基準は存在しません。一方で、刑罰の重さには大きな差があります。
- 危険運転致死罪:最高懲役20年
- 過失運転致死罪:最高懲役7年
このため、危険運転の適用対象にならず、遺族が不満を抱くケースも少なくありません。特に高速道路や市街地など条件が異なる状況では、何が危険運転にあたるのか判断が困難でした。
法制審で示された“速度・飲酒の数値基準案”
29日に示されたたたき台では、速度超過とアルコール摂取に関する具体的な数値が提示されました。
- 速度超過の基準案
- 最高速度70キロ以上の道路:最高速度を50キロ超える速度で運転した場合
- 最高速度60キロ以下の道路:最高速度を40キロ超える速度で運転した場合
- アルコール摂取の基準案
- 呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上のアルコール量
これにより、従来の「制御困難な高速度」という抽象的な表現が、より客観的に判断できる方向に変わる見込みです。
遺族からの期待と指摘
速度や飲酒の数値基準が示されたことについて、事故で夫を亡くした佐々木多恵子さんは次のようにコメントしています。
「数値基準がないと危険運転を立証するのは非常に難しい。控訴されると、加害者は『危険ではない』と主張できる。今後はこうした争点が整理され、同じような事故に苦しむ遺族の負担が軽減されるはずです」
一方で、遺族からは「住宅地や学校の近くでは、もう少し低い速度でも危険運転と認定すべき」という意見もあり、数値だけでは判断が不十分なケースもあると指摘されています。
まとめポイント
- 過失運転致死罪と危険運転致死罪の線引きは曖昧で、遺族から改善を求める声が長年あった。
- 速度超過や飲酒量の数値基準が法制審で示され、危険運転の客観的な判断材料が整いつつある。
- 数値基準の導入により、控訴審などで加害者が危険運転を否定する争点が減少する可能性がある。
- 遺族からは「数値だけでは不十分で、状況や地域に応じた判断も必要」との指摘がある。
- 今後の法改正や運用次第で、危険運転致死罪の適用の透明性と被害者救済の実効性が高まることが期待される。