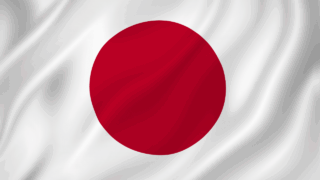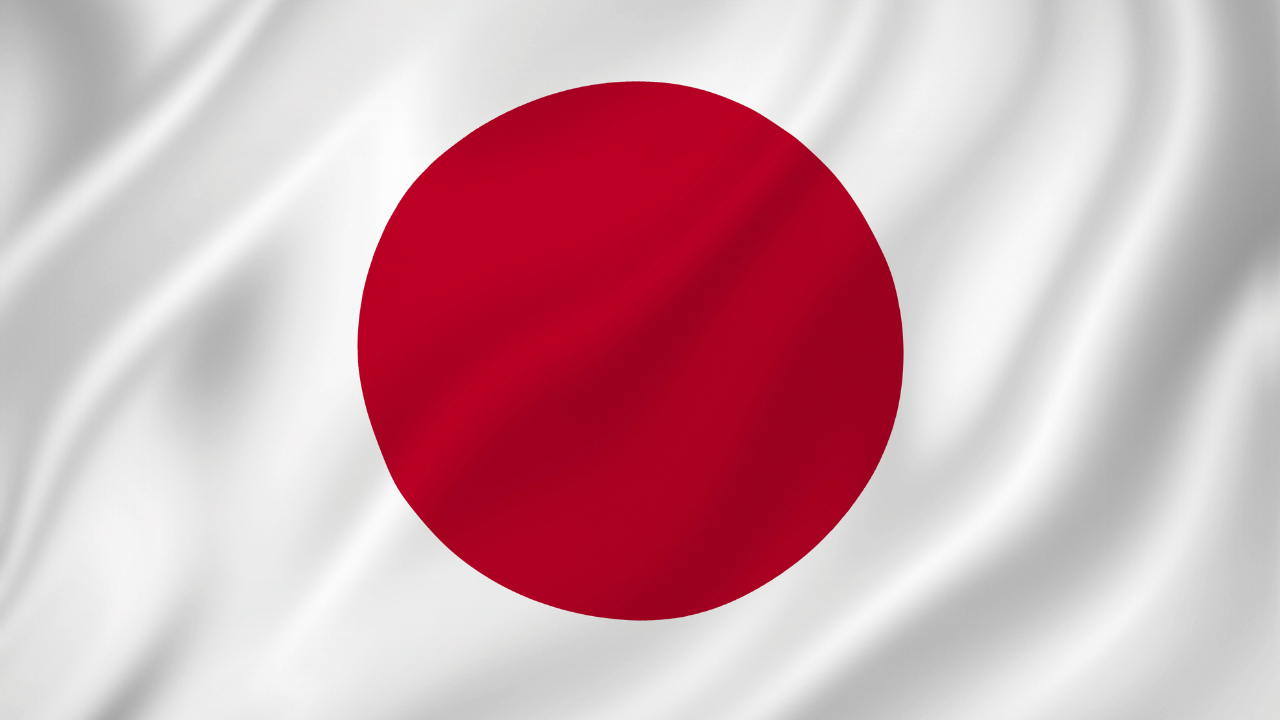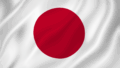「令和の米騒動」再び
2024年から2025年にかけて、日本の米市場はかつてない混乱に直面しています。店頭からコメが姿を消し、スーパーやコンビニでは価格が跳ね上がる異常事態が続いており、一部では「令和の米騒動」とまで呼ばれています。
農林水産省は「秋の新米が出回れば価格は落ち着く」と見ていましたが、実際には2025年1月時点で東京23区の消費者物価指数におけるコメ類の価格が前年の1.7倍に上昇。全国的にも過去最大級の上昇幅となり、国民の生活を直撃しました。
コメ不足は本当に起きているのか?
生産量自体は減っていません。2024年産米の主食用収穫量は679万トンと前年より18万トンも多く、国内需要を十分に満たせる水準です。にもかかわらず、JAなど主要な集荷業者が確保した量は前年より20万トン以上減少。
このギャップが「コメ不足」騒動を招きました。要因の一つは、生産者や一部流通業者による“抱え込み”です。品薄を受けて価格上昇を期待したり、直販需要を見込んで出荷を抑える動きが広がったのです。
卸売価格と小売価格への波及
JAが生産者に支払う概算金は前年の約1.5倍まで引き上げられました。しかし、それでも十分に集荷できず、卸売市場での相対価格は急騰。さらに、業者同士のスポット取引では、価格が2024年の3倍に迫る異常水準となりました。
その影響は最終消費者にも直撃。スーパーの米袋価格や、コンビニのおにぎりの値上げとして表れ、消費者の不満が高まっています。
農水省の対応 ― 備蓄米の放出
こうした状況を受け、農水省は本来「大凶作時」しか認められていなかった備蓄米の放出に踏み切りました。さらに、放出した量は1年以内に買い戻すという条件をつけ、需給調整の仕組みを構築。
この発表だけで市場の過熱は一時的に沈静化し、「口先介入」のような効果を発揮しました。ただし、抱え込み米がどれほど市場に流れるかは未知数で、根本的な不安は残ります。
今秋は「一転コメ余り」の可能性
注目されるのは2025年産米の行方です。専門家によれば、今年はむしろ「過剰生産」に傾く可能性が高いといいます。
その理由は2つあります。
- 備蓄米の買い戻し
今年放出された備蓄米は翌年買い戻されるため、2025年産の需要が増加。結果的に生産者の増産意欲を刺激します。 - 用途変更の柔軟化
収穫前の段階でも、飼料用や輸出用として申請したコメを主食用に振り向けられる制度が整備されつつあります。これにより、品薄時には主食用米が増産され、逆に余剰時には他用途に回せる仕組みが稼働することになります。
農政転換と水田政策の課題
一方で、今回の騒動は農業政策全体の転換点にもつながっています。これまで日本の農政は「水田を維持すること」を中心に据えてきましたが、その象徴だった「水張り5年ルール」が2027年度から撤廃される方針です。
今後は水田だけでなく、麦・大豆・飼料作物といった輸入依存度の高い品目も含めた支援へと拡大する予定です。ただし、その分財政負担の増加は避けられず、持続可能な農政のあり方が問われています。
専門家の視点 ― 生産調整の本当の姿
宇都宮大学の小川真如助教は「生産調整=減反」と単純化されがちだが、本来は需要に応じて生産を増やしたり減らしたりする柔軟な仕組みであると指摘します。
2025年はまさに「増産局面」であり、需給見通しをにらんで農業再生協議会が作付け目安を積み増している状況です。農家もコメ作りから撤退せず、生産を維持・拡大する動きが強まると予想されます。
まとめのポイント
- 2024年の「令和の米騒動」は、実際には生産不足ではなく流通の抱え込みや投機的な動きが要因。
- 農水省は備蓄米の放出や用途変更の柔軟化で需給調整を図り、市場の混乱を抑制。
- 2025年は一転して「コメ余り」になる可能性が高く、価格安定の一方で補助金負担の増加が課題に。
- 日本の農政は水田中心から麦・大豆・飼料作物を含めた食料安全保障強化へシフトしつつある。
米価格の乱高下は家計を直撃するだけでなく、農業政策そのものの転換点を浮き彫りにしています。今後のコメ市場をめぐる動きは、消費者・生産者双方にとって見逃せないテーマといえるでしょう。