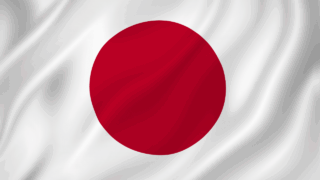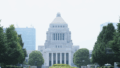日本の消費税は、私たちの生活に深く関わる税金ですが、経済学の観点から「本当に必要な税金なのか」と疑問を呈する声もあります。特に近年注目を集めているのが、現代貨幣理論(MMT)を提唱するステファニー・ケルトン教授の視点です。彼女は2019年に来日した際、日本の消費増税について批判的な見解を示しました。その理由をわかりやすく整理してみましょう。
1. 日本はインフレに悩んでいなかった
消費税は一般的に政府の財政を支えるための税金ですが、MMTの考え方では、税金の最も重要な役割は「インフレの抑制」にあるとされます。
当時の日本は、むしろ物価がほとんど上がらないデフレ気味の状態でした。ケルトン教授は、インフレの問題がない状況での消費税増税は、経済にとって逆効果だと指摘しています。つまり、「インフレを抑える必要がないのに税金を増やす」ということは、経済を無駄に冷やす行為になってしまう、というわけです。
2. 景気を冷やし、消費者の不安を招く
消費税が上がると、私たちの手元に残るお金が減ります。これは単純に購買力を奪うことにつながり、消費者が「お金を使うのを控えよう」と考える原因になります。
結果として、経済活動が鈍化し、景気の低迷をさらに悪化させる恐れがあります。ケルトン教授は、こうした「景気に逆行する影響」を問題視しているのです。
3. 財政政策で積極的に経済を支えるべき
MMTでは、政府は自国通貨を自由に発行できるため、財源不足に悩む必要はないと考えます。そのため、政府が目指すべきは財政収支の黒字化ではなく、国民の雇用や生活水準の向上です。
消費税の増税は、このような積極的な財政政策と相反する可能性があります。必要以上に税金を取ることで、経済の成長や雇用創出のチャンスを阻むことになりかねない、というのがケルトン教授の立場です。
4. 現代貨幣理論(MMT)の視点とは
MMTは少し難しい理論ですが、簡単に言うと「自国通貨を発行できる国は、財政破綻を心配せずに必要な支出を行える」という考え方です。
日本のように自国通貨である円を発行できる国の場合、政府は十分な資金を国民生活や雇用のために投入することが可能です。そのため、無理に消費税を増やす必要はない、というのがMMTに基づく主張です。
5. MMTと消費税をめぐる議論
MMTの考え方は世界中で議論を呼んでいます。日本でもコロナ禍以降、財政政策のあり方を見直す動きの中で、MMTを根拠に「消費税は減税すべき」という意見がSNSやメディアで再び注目されています。
一方で、伝統的な経済学の観点からは「インフレリスクを無視できない」といった批判もあります。つまり、MMTの主張は全ての経済学者に受け入れられているわけではなく、議論の余地があるテーマなのです。
まとめ
ケルトン教授の視点を踏まえると、日本の消費増税にはいくつかの問題点があることが見えてきます。
- インフレの心配がない状況での増税は意味が薄い
- 消費者の不安を煽り、景気を冷やす可能性がある
- 積極的な財政政策の妨げになる
MMTはまだ新しい考え方ですが、私たちの税金や財政政策の在り方を考える上で重要なヒントを与えてくれます。今だからこそ、消費税や政府の財政政策を改めて見直すきっかけになるでしょう。