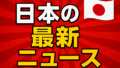■ なぜこのニュースが重要なのか
全国でクマによる被害が増加しています。死者数は統計開始以来の最多となり、岩手県や群馬県では日常生活やレジャー中に襲われるケースも発生しました。
政府は、市町村の判断で生活圏に出没したクマを駆除できる「緊急銃猟」制度を導入しました。しかし、現場のハンターには「安全に発砲できるか不安」といった戸惑いもあり、制度運用の難しさが浮き彫りになっています。
私たちにとっても、身近な生活環境で自然と人間がどう共存していくかを考えるきっかけになるニュースです。
■ クマの増加と行動の変化
酪農学園大学の伊吾田宏正准教授によると、過去30年間でヒグマの個体数は約2倍に増加。ツキノワグマも分布域が広がり、個体数が増えている可能性があります。
同時に、人を恐れないクマも増えています。これは「個体数の増加」と「クマの行動の変化」の両方が原因で、出没や被害の増加につながっています。
特に秋は、冬眠前で大量の食料が必要な時期。ドングリなどが不作だと、農作物や人の生活圏に侵入するケースが増えます。兵庫県立大の横山真弓教授の調査では、クマ出没時に**柿が誘因になっているケースは71%**に上ります。
■ 遭遇時の基本対応と注意点
栃木県猟友会の小堀大助事務局長によれば、クマと遭遇した際の基本対応は以下の通りです。
- 目をそらさない
- 走らない
- じりじりと間合いを遠ざける
ただし、クマには個性があるため、臆病なものも好奇心旺盛なものもおり、対策はケースごとに変わります。
あなたが森でクマに出会ったら、冷静に距離を取り、安全な場所に退避することが大切です。
■ 緊急銃猟制度とは
2024年9月に改正された鳥獣保護法により、**市町村長の判断で生活圏に出没したクマを駆除できる「緊急銃猟」**が導入されました。
駆除の条件は以下の4点です。
- 住宅や公園など人の生活圏に侵入
- 人命や身体に対する危害が差し迫っている
- 銃猟以外の方法では捕獲が困難
- 弾丸が地域住民に届くおそれがない
これにより、従来は県知事や警察官の指示が必要だった発砲判断が迅速化されました。
■ 制度の現場運用とハンターの負担
栃木県猟友会では、通報から発砲までの訓練を行い、30分以上かかることがわかりました。現場では高度なスキルを持ったハンターが必要ですが、会員全員が十分な経験を持つわけではありません。
また、ハンターが駆除を行った際に物損や事故が発生すると、市町村や国家賠償制度が適用されるものの、精神的な負担や非難の声が大きな課題となっています。
■ 駆除だけに頼らない総合的な対策が必要
専門家は、駆除は「最終手段」とし、まずは出没を防ぐ努力を徹底すべきだと指摘しています。
- クマの通り道の茂みを刈り払う
- 出没情報を迅速に共有する
- 農地や公園への電子柵やドローンによる追い払い
- 個体数が多い地域での管理
これらの総合的な対策があってこそ、人とクマの共存が可能となります。
■ まとめポイント
- 全国でクマ被害の死者が過去最多となり、緊急銃猟制度が導入
- 秋は冬眠前で食料確保のためクマの出没が増加、柿などが誘引になる
- 遭遇時は冷静に距離を取り、安全な場所へ退避することが重要
- 緊急銃猟は「最終手段」であり、駆除にはハンターの高度な技術と負担が伴う
- 駆除だけに頼らず、電子柵や茂みの管理など総合的な対応が必要
(出典:Yahoo!ニュース「クマ被害の死者“過去最多” 新制度“緊急銃猟”…現場には戸惑いも 「人命最優先で駆除」なのに抗議…ハンターのやりきれない思い」